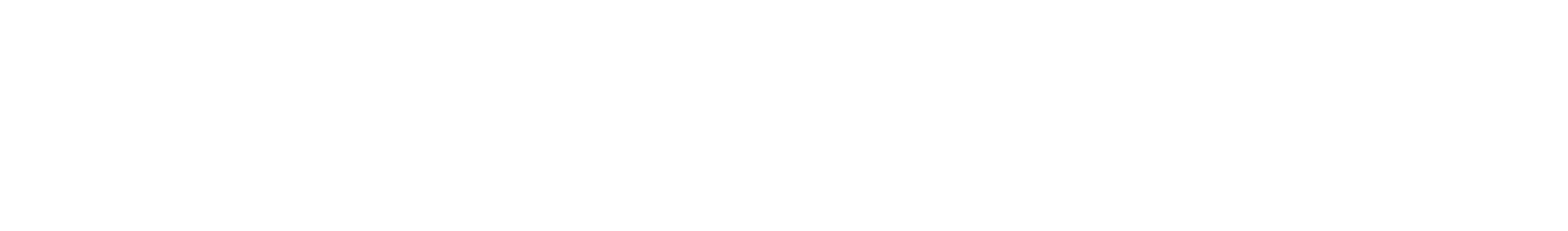テックねこです!
あなたはこんな悩みを持っていませんか?
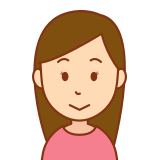
RPAを導入したいけど、どの業務から取り組んだらいいか分からない。
この記事では、業務を自動化する際の判断基準をまとめてみました。記事の最後にその業務がRPAに向いているかの判断に便利なチェックリストを用意しています。ぜひご覧ください。
RPA化による効果があるか
RPAツールをつくるコストより自動化の効果が大きい場合、RPA化による効果があるといえます。例として以下のようなものがあげられます。
RPAツールをつくるコストの例
- RPAツールをつくる人件費
- RPAライセンス料金
- パソコン、サーバ購入費
RPA導入による効果の例
- ミスの削減
- 手戻りがなくなる
- 残業時間の削減
- RPAで業務が減った分新しい業務ができるようになり利益向上につながる

RPAツールを作成する際は効果の大きい業務から作成しましょう。
技術的にRPA化可能であるか
基本的には、RPAツール作成者に技術的に可能かどうか判断してもらうのがよいでしょう。厳密に判定するには時間がかかるので、業務選定段階では簡単な判定で大丈夫です。
技術的に可能かどうかの判断基準について簡単にいうと、RPAが苦手な作業が少ないほど実現度が高いです。
RPAが苦手な作業
- 業務ルールがあいまいである。
- 臨機応変な判断が必要な処理がある。
- 業務ルールやシステム、画面の変更が頻繁にある。
RPAが得意な作業
- ルールがしっかり決まっている。どのような場合に何をするかが明確である。
- 業務ルールやシステム、画面の変更がほとんどない。
- 文字列や表データからデータ読み取りをする。
- webブラウザ上の処理、エクセル上の処理、コマンド実行などで実現できる処理である。
RPAが予期しない動作をした場合、修正などの対処が可能であるか
RPAが予期しない動作をした場合、検知可能か、修正可能であるかは重要です。必ず確認しておきましょう。
検知可能かどうかは技術的な部分になるので、RPAツール作成者に相談しましょう。
手作業で修正可能なのであれば問題ありませんが、大量の人数が必要になる場合は事前に体制を決めておきましょう。パッチを当てて1発で修正可能な場合は、問題発生時の連絡先や対応部署を明確にしておきましょう。
人がしなければならない業務ではないか
例えば勤務申請の承認業務などは、人がやらなくてはいけない業務です。すべての勤務申請をRPAで承認してしまったら、残業してないのに残業申請して不当に給料を得る社員が出てきてしまいます。
原則、承認行為などの人がやるべき業務はRPA化してはいけません。
対象のシステムはツールによる自動化を許可しているか
業務で用いるシステムは、RPAツールの利用の許可を得ましょう。許可なくRPAツールを作成してはいけません。「データを見るだけだから、そんなにシステムに負担がかかる業務ではないから…」といって無許可で自動化するのは推奨しません。
RPAではありませんが、自動ツールの実行で逮捕に繋がった事件があります。この事件は、本人に悪意はなく、実行したツールもシステムに負荷をかけないように作成していました。(岡崎市立中央図書館事件、Librahack事件)
企業で上記のような事件を起こせば損害賠償や信用の失墜など大きな損失に繋がります。必ず、対象システムでRPA実行をして良いか許可を取りましょう。
RPA用のアカウントは用意できるか
対象システムでログインが必要であれば、RPA用のアカウントを用意しましょう。万が一RPAが暴走した場合も問題の切り分けや修正が容易になります。RPA用アカウントが決まっていれば、監視も容易です。
何らかの理由で、RPA用アカウントが取得できない場合は、対象システムの管理者に許可を取りましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
業務がRPAに向いているかの判断に便利なチェックリストを用意しました。ぜひ参考にしてみてください。
▼本気でRPAをマスターしたいならこちらをチェック
 Copyright secured by Digiprove © 2019
Copyright secured by Digiprove © 2019